「無料で使える生成AIツールはあるけど、どれがいいのかわからない…」
「そもそもどんなメリットがあるの?」
「どのような場面で活用できるのか知りたい!」
生成AIツールで文章を作成するにあたり、疑問を抱えている方は多いでしょう。
生成AIツールは年々進化しており、特に近年では人が書いたものと区別がつかないような文章を生成してくれます。無料で使えるものも多く、ビジネスのあらゆる場面でも活用できることから、AIの導入を検討している企業も少なくありません。うまく活用することで、社内資料やメール作成など、日常的な業務を効率よく行えます。
しかし、文章生成AIのツールが増えてきたことから「どれを使えばいいの?」と悩む人もいるでしょう。また、文章生成AIの効果的な活用方法を知らずに使っている人もいるかもしれません。
この記事では、生成AIツールによる文章作成について以下の内容を解説します。
- 無料で使える文章生成AIのおすすめ
- 文章生成AIを使うメリット
- 文章生成AIを使うデメリットと注意点
- 文章生成AIの活用事例
おすすめツールから活用方法まで、幅広く解説します。無料で文章生成AIツールに触れてみたい人は、ぜひ最後までお読みください。
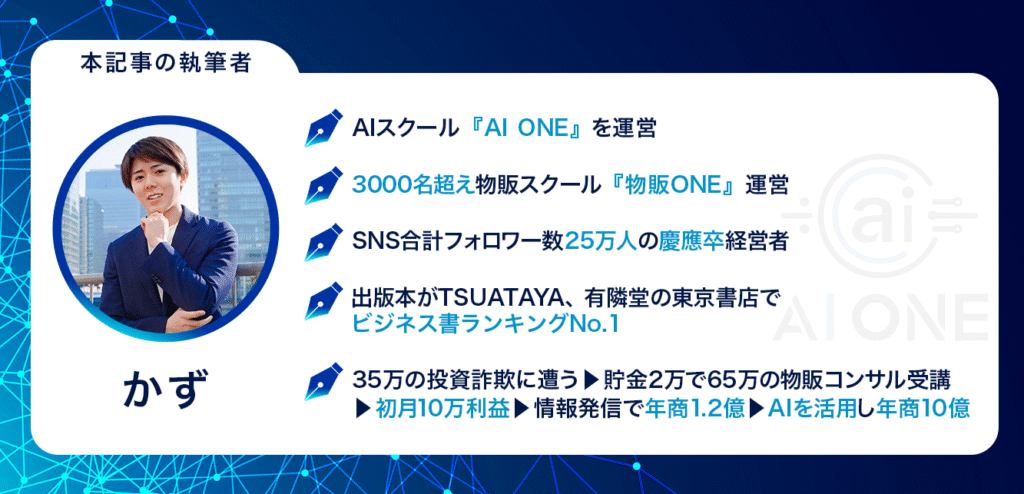
-1024x645.png)
無料で使える文章生成AIのおすすめ5選

まずは、無料で使えるおすすめの文章生成AIツールを5つ紹介します。
- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- Microsoft Copilot
- Copy.ai
どの生成AIツールを使おうか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。
1. ChatGPT
ChatGPTは、アメリカの企業OpenAIが開発した高性能のAIチャットボットです。
文章作成だけではなく、アイデア出しや長文の要約なども得意としています。例えば、報告書のたたき台作成や会議の議事録を要約したいときなどに役立ちます。
2025年4月現在、最新のGPT-4oモデルも無料で利用可能です。しかし、無料版には回数や文字数に制限があるため、仕事で頻繁に使うのであれば有料版を検討するとよいでしょう。
2. Claude
スタートアップ企業のAnthropic社が開発した生成AIツールがClaudeです。Anthropic社は、ChatGPTを開発したOpenAIの元社員が設立した企業です。
文章生成能力がとても高く、人間が書いたものと見分けがつきにくいほど自然なテキストの生成が可能です。Claudeは特に自然言語処理能力に優れているため、文章作成の分野で高い性能を発揮します。
小説のようなクリエイティブなものから、メールや説明文などビジネス的な文章まで、多様なジャンルの文章生成が可能です。また、設計段階から安全性と倫理的な側面に配慮されているため、有害な内容や偏った情報の生成を防いでくれます。
3. Gemini
Geminiは、検索エンジンでおなじみのGoogleが提供している対話型AIサービスです。
Googleアカウントを持っていれば、無料で文章の生成や要約など基本的な機能を利用できます。文章の長さやトーンなどを細かくカスタマイズできるため、目的や用途に応じてさまざまな使い方ができます。
また、Google検索を通じて最新情報にアクセスできるため、より正確で新しい回答の生成が可能です。リアルタイムの情報を得られるため、回答精度は高いと言えるでしょう。
さらに、Geminiはマルチモーダル生成AIが搭載されており、テキスト以外にも画像や動画など複数のデータを同時に処理できます。テキスト以外のファイルを活用して資料を作り上げたい人に、おすすめのツールです。
4. Microsoft Copilot
「Microsoft Copilot」はWindows OSやWord, ExcelなどのOfficeソフトで知られる、Microsoft社が提供する対話型のAIツールです。
Copilotは文章を生成できるほか、テキスト情報から画像を自動生成することも可能です。また、ChatGPTと同じ言語モデル「GPT」を使っています。そのため、精度や使いやすさはChatGPTと似ている部分が多いです。
なお、有料プランにアップグレードすることで、Microsoft 365との連携が可能です。テキストでの指示だけで、Wordでの文書作成やExcelの表作成が行えます。
5. Copy.ai
「Copy.ai」は広告やブログ、SNSの投稿などを効率よく作れる文章生成AIです。
商品やサービスの紹介文、Webサイトのキャッチフレーズなど、自然な表現で読みやすい文章を数秒で生成できます。例えば、商品のキャッチコピーやイベントの告知文などを何パターンも用意したい場合に便利です。
また、有料プランにアップグレードすると、90種類以上もある豊富なテンプレートを利用できます。テンプレートを活用すれば、文章作成のプロンプトを考える手間が省けるため、質の高いコンテンツを効率よく作成できるでしょう。
文章生成AIを使うメリット3選

生成AIツールのメリットを理解することで、文章作成が求められるあらゆる場面で使う意識が生まれるようになります。文章生成AIツールを使うメリットを3つ紹介します。
- 文章作成にかかる時間を短縮できる
- 新しいアイデアを創出できる
- 人的ミスを減らせる
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 文章作成にかかる時間を短縮できる
生成AIツールを活用することで、文章作成に費やす時間を短縮できます。
文章をゼロから書き始めると、多くの時間と集中力が必要です。疲労を感じると作業は滞るため、さらに時間がかかるでしょう。しかし、生成AIツールを活用すれば、たとえ長文だとしてもテーマや文字数などの条件を指示するだけで文章を作成できます。
例えば、1万文字程度のたたき台であれば、5分ほどで生成してくれます。AIによって生成された文章は調整や確認が必要であるものの、ゼロから文章を作成するよりも大幅に時間短縮が期待できるでしょう。
文章を作成する時間を短縮できれば、その分をより創造的な仕事へ回せるようになり、仕事全体の効率化につながります。
2. 新しいアイデアを創出できる
生成AIツールは、新たな発想を生み出す補助としても活用できます。
一人だけの考えでは、斬新な視点や切り口を発見するのは難しいものです。生成AIは自分ひとりでは思いつかないような発想や視点を、見つけられる可能性があります。
例えば、同じ意味の文書であっても、生成AIに書き換えてもらうことで別人が書いたような文体で出力してくれます。他にも、ブログ記事のタイトル案や新商品のキャッチコピーなどを複数出してもらうことで、アイデア出しの手助けになるでしょう。
自分にはない考え方や切り口を知ることで思考の枠が広がり、より独創的で質の高いコンテンツを生み出すきっかけが得られます。
3. 人的ミスを減らせる
AIは機械的に作業を行ってくれるため、人間が起こしやすいミスを減らせます。
人が文章を作成する場合、疲労や集中力の低下の関係から、確認漏れや誤字脱字などが発生しやすいです。しかし、AIは与えられた指示やルールに基づいて常に一貫性のある処理を行ってくれます。
例えば、報告書に記載されている数字に半角と全角が混じっているとします。この時にAIに「文章中の数字をすべて半角にしたい」と指示を出せば、既存の文章を修正してくれます。
人が不注意から起こしそうなミスを削減できるため、文章全体の正確性や品質の向上に貢献してくれるでしょう。
文章生成AIを使うデメリットと注意点5選

生成AIツールで文章を作成することで作業効率が上がるなどのメリットがあります。一方で、以下のようなデメリットも存在するため、理解しておきましょう。
- 文章のクオリティにばらつきがある
- 誤った情報が生成されることがある
- 日本語の使われ方が不自然な時がある
- 機密事項は入力しない
- 権利侵害に注意する
デメリットを理解したうえで文章を作成すれば、生成AIツールは大きな武器となるはずです。ひとつずつ見ていきましょう。
1. 文章のクオリティにばらつきがある
生成AIが出力する文章の品質は、一定ではなくばらつきがあります。生成AIの出力結果にばらつきがあることを「ハルシネーション」と言います。
ハルシネーションが起こる理由は、多くの文章生成AIツールが出力結果にある程度のランダム性を持たせるように設計されているためです。文章作成に用いる場合、同じ指示を入力しても毎回文体や言葉遣いが異なる文章が出力されます。
文章生成AIを業務で活用する際、出力結果にばらつきが生じるのは仕様と割り切りましょう。納得のいく出力結果が得られなかった場合は、同じ条件で再度出力してみると良いでしょう。
2. 誤った情報が生成されることがある
生成AIが出力する情報に誤りが含まれている場合があることは、利用するうえで最も注意すべき点です。
AIは、学習した膨大なデータを元に文章を生成します。生成AIツールが誤情報を出力する理由は、学習したデータそのものが誤りがあることが考えられます。
また、学習データに問題がなくてもAIが情報を誤って解釈してしまうと、誤情報が含まれた文章を出力してしまうケースも少なくありません。
生成AIツールで出力した文章は、ご自身の目でファクトチェックを行うようにしてください。とくに、統計データや正確性が求められる専門的な内容などは信頼できる情報源を参照し、事実確認を行いましょう。
3. 日本語の使われ方が不自然な時がある
人間が書いた文章と比較すると、不自然な言い回しや表現が含まれることがあります。
文法的に破綻していることや、意味が通じない日本語が出力されることは少ないです。しかし、文法的には正しくても、読みづらさや違和感を覚えるような不自然な表現が使われているケースがあります。
例えば「生活の不満を明確化するプロセスは、単なる現状分析を超えて、将来の住まいづくりへの重要な投資となります」といった文章です。意味を理解できる人は多いでしょうが、日常的には使われない表現が多く不自然な印象を持つでしょう。
違和感のある表現をそのまま使うと、読者に意図が伝わらない可能性があります。AIから出力された文章は必ず人の目で確認し、自然な表現に直しましょう。
4. 機密事項は入力しない
文章生成AIを利用する際には、入力する情報の内容に細心の注意が必要です。
多くのAIサービスでは、プロンプトがAIの学習データとして利用される可能性があります。機密性の高い情報を入力した場合、AIの学習データとして取り込まれてしまうかもしれません。
入力してはいけない情報の例として、顧客の住所や電話番号などの機密性の高いデータが挙げられます。学習データとして利用された場合、他のユーザーへの回答に出力される可能性があります。
生成AIツールで作成した文章を業務で利用する場合には、機密情報の取扱いを徹底してください。企業や組織として文章生成AIを活用する場合には、特に注意が必要です。
5. 権利侵害に注意する
著作権をはじめとする権利侵害にも注意が必要です。
生成AIが学習したデータには、Webサイトのテキストや小説などが含まれている可能性があります。既存の著作物との類似性や依拠性が認められるAI生成物を、著作者の許諾がないまま使用した場合、著作権を侵害する可能性があります。
AIが生成した文章が権利者の利益を不当に害すると判断された場合、損害賠償請求や利用の差止め請求を受けるリスクが懸念されます。
AIによって生成された文章を利用する際には、既存の著作物の権利を侵害していないか常に配慮が必要です。
文章生成AIの活用事例5選

生成AIツールで文章を作成できると言っても、実際にどのような場面で活用できるのかイメージが湧かない人も多いでしょう。そこでここからは、生成AIツールで作成した文章を活用する事例を5つ紹介します。
- 資料作成
- メール作成
- 長文の要約
- キャッチコピーの作成
- 誤字脱字の修正
生成AIツールで文章を作成し、業務の効率化にぜひ活用してみてください。
1. 資料作成
生成AIツールは社内で使用する報告書や企画書など、指定されたテーマやフォーマットに沿った資料作成で役立ちます。
人が手作業で資料を作成する場合、定型的な項目を毎回記述するのはとても手間に感じるものです。また、資料を作成する担当者によって、品質にばらつきが出やすいです。
しかし、AIを活用すれば一定レベルの品質を保った資料を短時間で生成できます。
例えば、プレゼンテーション資料では、概要を入力するだけで構成や内容のたたき台を作れます。資料作成にかかる工数を減らせれば空いた時間で他の業務を行えるので、より生産性向上につながるでしょう。
最終的な内容の確認や表現の調整などは人の手で行う必要があるものの、資料作成にかかる工数を大幅に削減できます。
2. メール作成
生成AIを活用することで、メール作成の手間を大きく省けます。
取引先とのやり取りや社内の連絡など、ある程度フォーマットが決まったメールを書く機会が多い人もいるでしょう。文章生成AIに伝えたい内容や相手との関係性を指示すれば、的確なメールの文案を短時間で出力してくれます。
例えば「上司に進捗報告するメール案を作成して」と指示を与えれば文案が生成されるため、必要に応じて修正を行えばメールが完成します。
定型的なメールでも、1日に何通も作成していれば多くの時間が必要です。メール作成にAIを活用すれば時間を短縮できるため、他の業務に集中できるようになります。
3. 長文の要約
長い文章や複雑な内容から要点を簡潔にまとめる際に、文章生成AIが役立ちます。
情報量の多い資料や報告書から概要を掴みたい場合、自分で全部読むには多くの時間が必要です。そこでAIに要約を頼めば、全体を把握して要点だけをコンパクトにまとめてくれます。
例えば「学術論文Aを300字で要約して」と指示を与えれば、学術論文Aの重要なポイントを抽出し、要約文を作成してくれます。読解に時間がかかる長文でも、AIの要約機能を使えば効率よく概要を理解できるでしょう。
4. キャッチコピーの作成
商品やサービスの魅力を伝えるキャッチコピーも、文章生成AIを使えば効率よく作成できます。
短く印象的な言葉で商品やサービスの魅力を伝えることは難しく、数十時間かかることも珍しくありません。AIは毎回異なる結果を出力するため、多様な切り口からキャッチコピーの案を複数生成してくれます。
また、一人で考えていると無意識のうちにワンパターンになりがちです。キャッチコピー作りに文章生成AIを使うことは、アイデア出しの補助だけではなく、マンネリ化を防ぐうえでも非常に効果的です。
AIの案と自分のアイデアを組み合わせることで、より魅力的なキャッチコピーを作れるでしょう。
5. 誤字脱字の修正
人間が見落としてしまうような誤字脱字でも、AIであれば簡単に見つけてくれます。
人が文章を確認する場合、どれだけ注意しても見落としてしまうことがあります。特に長文になるほど集中力の低下や疲労などにより、確認の精度が落ちやすいです。
例えば1万文字の長文の中から、文章中で使われている全角の「AI」をすべて半角の「AI」に統一する、といった使い方です。
文章生成AIには、疲労や集中力のムラがありません。常に一定レベルの品質を保ったままチェックしてくれるため、文章の品質を一定レベルに担保できます。
文章生成AIのクオリティは無料でも実用的
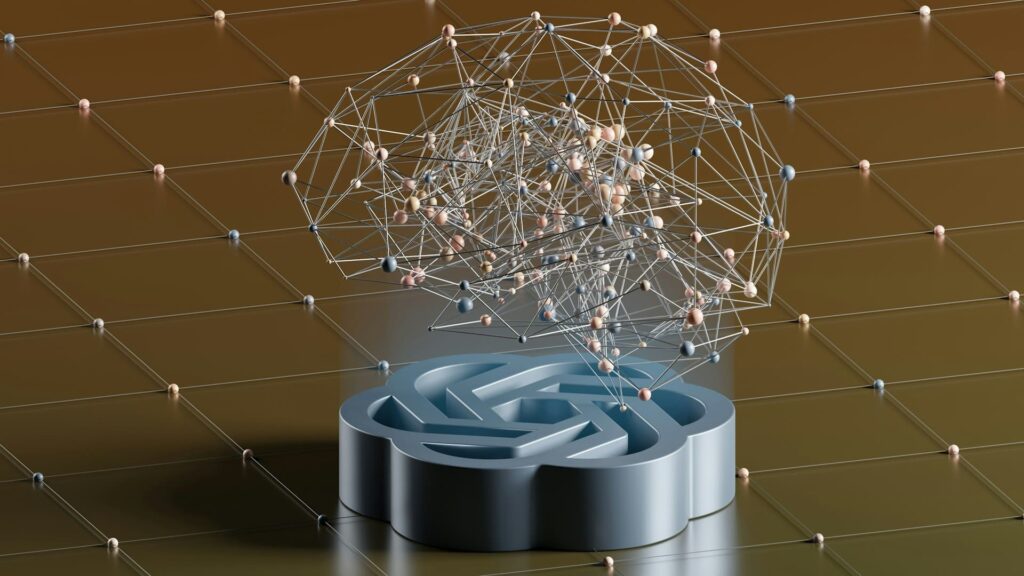
無料で提供されている文章生成AIツールでも、実用的なレベルの文章を作成する能力を持っています。例えば「ChatGPT」や「Gemini」などは無料で使えるプランが存在し、資料のたたき台作成や長文の要約など、幅広い用途で活用されています。
有料版と比較すると、生成できる利用回数や使える機能などに制限が設けられている場合が多いです。しかし、無料版でも十分なクオリティの文章を生成してくれます。「無料の文章生成AIの使い勝手を試してみたい」という人は、一度試してみることがおすすめです。
なお、AIの出力結果には、誤った情報が含まれていることや、日本語の表現が不自然だったりすることなどがあります。AIにすべてを任せるのではなく、最終的には必ず人の目で内容を確認してください。
また、AIを効果的に使うにあたり効果的なのは、他人の使い方を知ることもひとつです。身の回りの人と使い方を共有することで、自分では思いつかない使い方を知れるかもしれません。
幅広いレベルの受講生が集うオンラインスクール「AI ONE」では、毎日多くの活用事例が寄せられています。「文章生成AIの効果的な使い方を学びたい」とお考えの人は、ぜひAI ONEの受講をご検討ください。
-1024x645.png)
 AI ONE
AI ONE 

